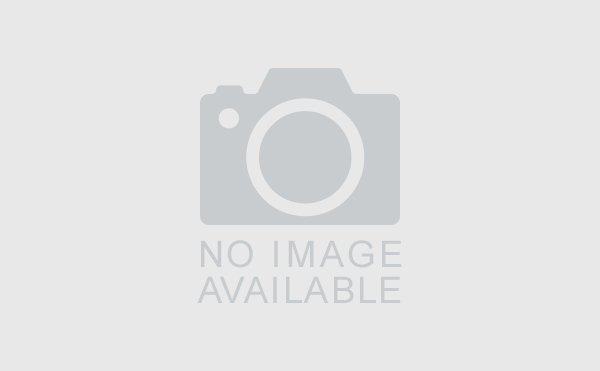210909 水島広子 / 『自己肯定感、持っていますか?』2 読書グラフィ 今日読んだ本
読書グラフィ 今日読んだ本
★水島広子 / 『自己肯定感、持っていますか? あなたの世界をガラリと変える、たったひとつの方法』
●
「どうしたら自分を好きになれるだろう」などと考えても、
自己肯定感は高まらないと思います。
なぜかと言うと、結局は「ありのまま」を受け入れていないからです。
「自分を好きになりたい」ということは、
「今の自分が嫌い」ということです。
「自分が嫌い」というところの上に何を積み重ねていっても、
パラダイム・シフトは起こせないと思います。
ですから、自分の「ありのまま」を受け入れることは必要条件なのです。
●自己認識より他人についての認識を変化させるほうが簡単。
「自分」に目を向けている限り、自己否定しか出てこないかもしれませんが、
「相手」に目を向けて、相手をリスペクトしていくと、
その「リスペクト感」が自分にも及んでくるものです。
「リスペクトの空気」を一緒に吸うという感じ。
「人間、みんな頑張っているな」という感覚。
●周りへの対応が自分に返ってくる。
●(行動するとき、)
自分の優しさや温かさを感じながら行なうことができたほうが、
自己肯定感は高まっていくはずです。
人に何か注意をしなければならない場合、
「まったく、あなたはいつもこうなんだから」という姿勢で
イライラしながら注意するのか、
「よく頑張っていると思うけれども、ここのところは気をつけてね。
間違いやすいところだから」という姿勢で穏やかに注意するのかで、
「自分についての感じ」はずいぶん違ってくるでしょう。
●自分から有害ガスが吹き出したら、
それを自らも吸い込むことになるのと同じで、
よい雰囲気を醸し出すことができれば、
自分自身もその「よい雰囲気」の恩恵にあずかることができるのです。
●自分自身のことも、
「いろいろと事情がある中で、頑張っている存在」として見てあげることです。
●「ダメな自分」にも”事情”がある。
「ダメだ」より「大変だったね」と自分に言う。
●自己肯定感の低い人が何を基準に行動するのかと言うと、
自分の「したい」ではなく、「べき」。
相手の顔色を見て「この人を喜ばせるには、○○すべき」と考えたり、
「人間として受け入れられるためにはXXすべき」と考えたりするのです。
そこには、「したい」という主体的な思いはなく、
ただ、他人の顔色や「世間」「常識」に流されているだけ、と言えます。
つねに「ありのまま」は否定され、「べき」で塗り替えられてしまう。
また、「べき」で生きていると、
他人にも「べき」を要求するようになっていきます。
●自分の「したい」を中心に考えられるようになると、
「べき」との関係が切れてきます。
主体が自分になるからです。
自己肯定感がある程度高ければ、自分不在の「べき」よりも、
自分が主体の「したい」を中心に考えられるようになるのです。
そして、「したい」に基づいて行動すると、達成感が得られますから、
ますます自己肯定感が高まる、という好循環に入ることができます。
●悪い「条件」の中でも生きてきた自分、頑張ってきた自分こそ、
リスペクトすることができるのです。
●ここまで生き延びてきた自分を愛おしむ。
●心の病を抱える人たちは、その多くが、
実際に「対人関係の問題」を”抱えていません”。
むしろ、「対人関係の問題」を起こさないように、自分を抑え、
周囲に気を使い、頑張ってきた人たちなのです。
●「ありのまま」を受け止められた体験が病を治す。
●アティテューディナル・ヒーリング(AH)
心の平和を唯一の目的とし、
自分の責任で心の姿勢(アティテュード)を選び取っていくというプロセス。
(参考:http://www.ah-japan.com/whatisAH.htm)
●安全な環境とは、自分に評価を下されない場所。
●誰かの陰口を聴かされたときに、「同調」してしまうと、
ますます嫌な気持ちになってしまいます。
そんなときは、「同調」するのではなく、
「いろいろ大変だねぇ」「そうか、よく頑張ったね」などと
「相手]の「大変な話」として聴くのです。
仮に同調を求められたとしても、「同調しなくちゃ」と思うのではなく、
「今は同調を求めたくなる気持ちなんだね」と
「相手の領域」の「ありのまま」を受け入れるだけで十分なのです。
あくまでも「相手の感想」ととらえる。
●思春期になると、
親にとっては「子供の領域は、子どものもの」という意識を持つことが、
ひとつの課題です。
「まあ、あの子ももう大人だから・・・」と思えることが「子離れ」と言える。
●まずは、お互いの「領域」を守る伝え方をしましょう。
「そういうふうに言わないで」「どうしてそういうことを言うの?」と
「相手」について話すのではなく、
「そういうふうに言われると悲しい」と「自分」の気持ちについて話すのです。
「家族だから何を言ってもよい」のではなく、
「家族だからこそ『領域』に気をつけたものの言い方が必要」だと言えます。
●相手が何かを話してくれるのであれば、
思い込みや決めつけを手放して、ただその話を聴いてあげるとよいでしょう。
基本は「相手の内心は相手にしかわからない」ということでしょう。
そして、こちらに見えるのは、相手の言動だけです。
大変な時期を過ごしている相手を、ただ「見守る」。
何かを話してくれるのなら、「決めつけ」を手放してよく聴く。
また、相手が明るく過ごすことを求めてくるのなら、一緒に明るく過ごす。
そんなふうに、相手が過ごしたい形で一緒に過ごしてあげることができれば、
何よりでしょう。
●よかれと思って相手を変えたくなるとき
リスペクトの原則「相手を変えようとしない」
相手をリスペクトしつつ、
「心配だから、変えたほうがよいと私は思う」と、
あくまでも「自分の領域」で話をするとよいでしょう。
●相手が許してくれないとき
自分にできる限り誠実に謝ったら、あとは相手のペースに任せましょう。
自分ができることをしたら、後は気にしない。
●相手の「ありのまま」を受け入れ、
「でもよく頑張っているよね」などと言ってあげることは、
相手を生き返らせる効果があります。
成果ばかりを気にしている相手に対して、
「頑張っている」ことをリスペクトしてあげると、
大きな「安全」と「温かさ」をもたらすのです。
「そうだな、自分は頑張っているんだ」「まあ、なんとかなるかな」
というような安定感が得られると思います。
●自己肯定感の低い人の話を聴けば、
そこには必ず否定的な「決めつけ」を見つけることができます。
人間について、よく「丸くなる」という言葉が使われますが、
歳や経験を重ねることによって、
「人はそれぞれなんだなあ」ということを実感していくと、
決めつけなくなっていくでしょう。
決めつけない人は「寛大で、人間ができている」
というふうに見えるのですが、
それは特別なことではなく、人間が本来持っていたものなのです。
自分を傷つけ縛りつけてきた「決めつけ」を、
ひとつひとつ外していくことによって、本来の自分の姿が現れてくるのだ、
とイメージしてください。
「リスペクトしなければならない」のではなく、
「力を抜けば、リスペクトできる」のです。
苦行の話ではなく、解放の話なのです。
●人に対してつい感情的になってしまってうまくリスペクトできなかったな、
と感じたら、そんな「自分の事情」を受け入れて、
それでも丁寧に生きていこうとしている自分をリスペクトすればよいのです。